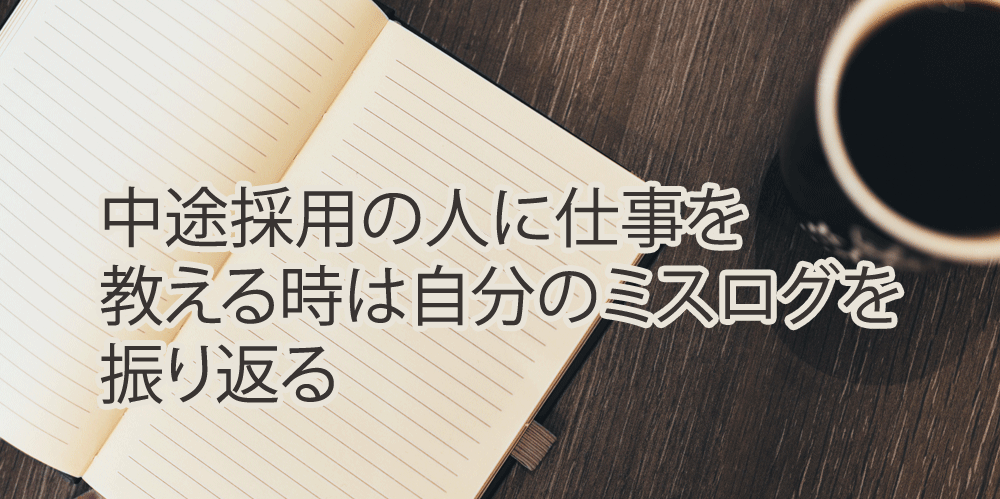「趣味は読書です」なんていうと、どんな作家が好きで何を読んでいるの?と聞かれることがあります。
読書と一口にいっても、これまた途方もなく広い世界で、お互いの好みが一致することはまずありません。多くの場合、そこで会話は途切れてしまいます。断絶した宇宙が人間と人間の間にもあるようです。
けれども、これから読書を始めてみたいという人には、この三島由紀夫の美しい星を今の私なら勧めるでしょう。
SF要素と人類存在への根源的な問いかけという2点を扱った作品。こ
の超絶的で骨太なストーリーをたった1冊で仕上げてしまう三島由紀夫の才能の凄さにとても驚いたと同時に、この美しく見通しの良い作品が読書の入門書としても最適ではないかと思われました。
あらすじ
『美しい星』は、三島文学の中では異色のSF的な空飛ぶ円盤や宇宙人を取り入れた作品で、執筆当時の東西冷戦時代の核兵器による人類滅亡の不安・世界終末観を背景に、宇宙的観点から見た人間の物語を描いている。作中後半の、人類滅亡を願う宇宙人と、滅亡の危機を救おうとする宇宙人との論戦が読みどころとなり、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』の大審問官的会話を意識して書いたことが、三島の創作ノートに記されている。三島37歳、長男・威一郎が誕生した年の作品である。
1962年(昭和37年)、文芸雑誌『新潮』1月号から11月号に連載され、同年10月20日に新潮社より単行本刊行された。文庫版は新潮文庫で刊行されている。
Wikipediaより
三島由紀夫がSF作品を書いたことに大変驚きました。天才はどんな具材も一流の作品に昇華することが出来ると聞いたことがありますが、それを地で行くような人物とはまさにこの人のことです。
物語の流れ
とある家族が自分たちは、地球とは別の天体から来た宇宙人であるという意識に目覚めるところから物語は始まります。
しかし、この宇宙人を自負する家族も宇宙人であるという自負が故に「かなり人間臭い」部分を露呈し、それと向き合い格闘していく過程が泥臭く描かれています。
またこの家族と対立する宇宙人が登場してきます。彼らの放つセリフは全く合理的で、私たちが日常的に社会から雛形として教え込まれている考えを深化させていくと、こういう考えにしか辿り着かないだろうなという最終形態をまざまざと見せつけてくれます。とくに『現代の悪』について語った部分が印象的です。
「悪はほとんど直接に血を見ず、衛生的な包装を施され、ひどく抽象的なものになりはしたが、その代わり誰も悪に本質的に関与することができなくなった。権力者たちでさえそうなのだ、悪のちゃんとした引き受け手、身元引受人はいなくなったのだ」
宇宙人という言葉の新しい定義
この「宇宙人」という言葉がとても面白いのですが、これが外からの視点を代弁者であるということが徐々に明らかになってきます。
最初のうちは、「宇宙人」を自認する家族が、善良な人がよく陥りがちな盲目の信仰。具体的に言うと、そうありたいと強く願ってしまったが故に仮想現実を個人の中に作り上げ、それを半ば強引に現実に適用するという事態に陥っているんだと感じます。
側から見ると、とても滑稽です。けれども、この「宇宙人」という言葉の意味が人間が扱う「核兵器」という言葉の刺激を受けて、段々と真剣味を帯びて読者に迫ってきます。この美しい星の中で言われる「宇宙人」と「円盤」は皆さんが普段感じているようなものとはまるで違う役を演じてくれます。
「宇宙人」を私たち茶化すことを三島由紀夫はよく知っていたのでしょう。さらに進めば、この「茶化す」という行為が実は人の持つ「冷たさ」に端を発しているとも言えないでしょうか。
SF作品を茶化すように、わたしたちは日々物事を茶化しながら、深刻な事態が個人の時間感覚ではなく、民族、国家の時間で刻々と進行していることをぼんやりとした頭で眺めています。
毎日メディアで話題に上るのは、ほとんど「人間のはなし」です。芸能人の話、スポーツ選手の話、政治家のスキャンダル、有名な占い師。会社に行けば、部下がいて、上司がいてお偉いさんがいてと、とにかく私たちの世界の中心に渦巻いているのは、常に人、人、人です。この美しい星に住みながらもそこから遠く隔たって、浮足だったような気持ちで切り刻まれる時間を脱する術が、この物語のクライマックスで明かされます。
木星から来た少し鈍い母親だけが、ぽつねんとした存在感を発揮しているところが胸に残っています。