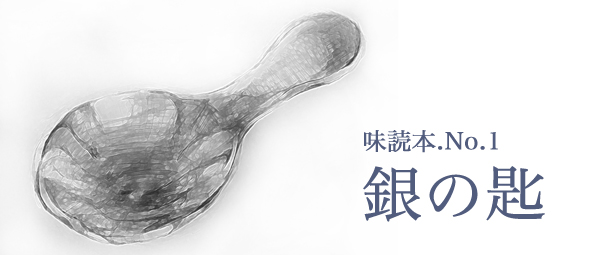山の頂から全てを見下ろすように、結末から逆算された書かれた作品は多いけれどこの作品はまるで違う。登りながらふと眼下の風景を眺めた時に、一つの完成を毎回丁寧に描ききっている。振り返った瞬間が常に「頂上」であるかのようにそれぞれの頂点がある。
かの夏目漱石も、「子供の体験を子供の体験としてこれほど真実にかきうる人は、実際他に見た事がない」とまで語っている。
子供の世界と大人の世界。人はそれぞれの都合からこれらをばっさりと切り分けてしまう。時代が進むほど、その溝は増々深くなっていくような気がしてならない。「銀の匙」はその間に横たわる深い溝に橋を掛けてくれる不思議な作品。
家族の話、友達の話、いじめの話、初恋の話、先生の話、兄弟の話、戦争の話など。これらが子供の視点から描かれている。ことに子供の視点が如実に書き現されていると感じたところは、蚕の話の部分。ここの描写には自分もはっとさせられた。
“蚕が老いて繭になり、繭がほどけて蝶になり、蝶が卵を生むのをみて私の智識は完成した。それはまことに不思議の謎の環であった。私は常にかような子供らしい驚嘆をもって自分の周囲を眺めたいと思う。”
ー本文より引用ー
この作品が発表されたのは大正時代だけれど、訳注もきめ細かく、また漢字のルビ振りも多いので、自分を含めて普段からあまり本を読まない人でもとても読み易い内容となっている。この本を読み終えた後に、緑帽子がトレードマークのノッポさんが、敬意を込めて、子どもたちを「小さい人」と呼んでいたことをふと思い出した。